お金を使ってしまう心理
マーケティング心理
人間が理性ではなく感性で動くことがよくわかる心理になります。ビジネスにおいて活用できるケース限られますが、経済的にも厳しい方でもお金を使ってしまう心理を解説します。
メンタルアカウンティング
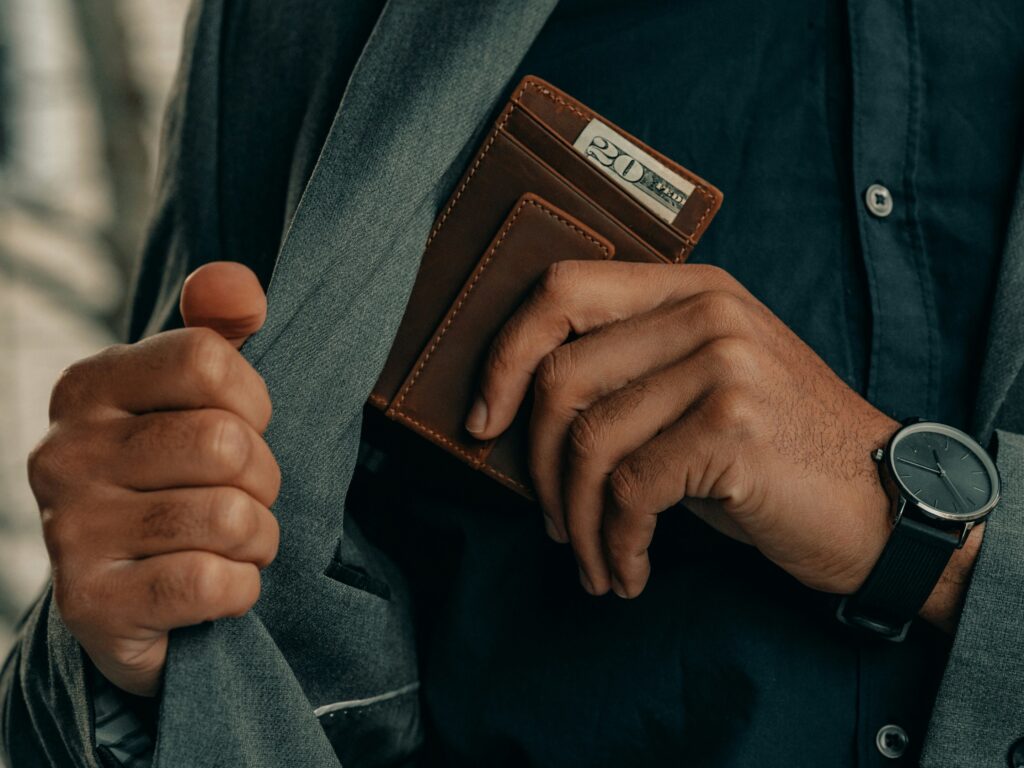
メンタルアカウンティングとは、心理学的な概念で、人々が金銭を異なるカテゴリーや用途に分けて管理し、支出や収入に対する感情的な反応を変えることを指します。この考え方により、個人は同じ金額でも異なる「口座」に入れることで、その使い方に対する評価や行動が変わります。例えば、ボーナスを「娯楽費」として扱う一方で、日常の生活費は慎重に管理する傾向があります。
使用場面
| 家庭の予算管理 | 家庭内で異なる支出カテゴリー(食費、娯楽費、貯蓄など)を設け、それぞれに予算を割り当てることで、消費行動を制御します。 |
| ギャンブルや宝くじ | 当選金やギャンブルで得た利益を特別な「娯楽口座」として扱い、通常の資金とは別に使う傾向があります。 |
| ボーナスや臨時収入の扱い | ボーナスを特別な支出に充てる一方で、通常の給与は生活費に使うことで、感情的な価値を分けます。 |
| 旅行資金の管理 | 旅行のために特別に貯めたお金を「旅行口座」に入れ、他の支出とは区別して使うことで、旅行をより楽しむことができます。 |
| 買い物の心理 | セールやポイント還元を利用する際、特定の商品の購入を「お得」と感じることで、無駄遣いを正当化する場合があります。 |
| 財務決定 | 投資や貯蓄の判断において、得られる利益をそれぞれの「アカウント」で異なる価値として評価し、リスクを取るかどうかを決定します。 |
成功させるコツ
メンタルアカウンティングをマーケティングで成功させるためのコツは以下の通りです。
1. ターゲットの明確化
顧客の異なるニーズや支出パターンに基づいて、セグメンテーションを行い、特定のグループに対してカスタマイズされたオファーを提供します。
2. 価格設定の戦略
製品やサービスに対して、心理的に納得感のある価格を設定します。例えば、特別なパッケージやセット販売を行い、購入を促します。
3. プロモーションの分割
セールやキャンペーンを期間限定で行い、顧客が特定の「アカウント」に予算を設定して支出を計画するよう促します。
4. ボーナスやポイント制度の活用
購入時にポイントや特典を付与し、それを「特別な資金」として扱わせることで、次回の購入を促します。
5. 購入体験の強調
特定の製品やサービスを購入することで得られる経験や感情的な価値を強調し、顧客にとっての特別な「アカウント」を作ります。
6. リマインダーの活用
定期的に顧客に対して特別なオファーやセールを通知し、予算を使う機会を提供します。
7. ストーリーテリング
商品やサービスの価値を伝えるストーリーを用いることで、顧客が購入後にどのような感情や体験を得られるかを想像させ、メンタルアカウンティングを活用します。
8. 顧客のフィードバックを重視
購入後のアンケートやレビューを通じて顧客の反応を収集し、メンタルアカウンティングの理解を深め、マーケティング戦略を改善します。
ハウスマネー効果

不労所得や臨時収入といった突然手にしたお金は、自分で労して稼いだ収入と比べて大胆な使い方をしやすい傾向。「ハウス」とはカジノなどの賭博場の意味で、そのカジノで扱うお金やチップである「ハウスマネー」になぞらえて、カジノで得た利益はリスキーかつ大胆に浪費しやすいことに由来しています。
使用場面
| ギャンブルやカジノ | 勝利して得たお金を「自分のお金ではない」と感じ、より大胆な賭けをする心理が働きます。この効果により、勝利金が消費されやすくなります。 |
| 株式投資やトレーディング | 投資で得た利益を、リスクの高い投資に再度使うケースがあります。投資家は、得た利益を「元手とは別のもの」と認識し、リスクを取りやすくなります。 |
| ボーナスや臨時収入の消費 | ボーナスや宝くじの当選金など、日常の収入とは異なる「特別なお金」を得たとき、そのお金を普段よりも気軽に使ってしまうことがあります。 |
| 企業のプロモーションやキャンペーン | キャッシュバックやクーポンを提供するキャンペーンでは、消費者が「タダで得たお金」としてそれを使い、余分な買い物をする傾向が見られます。 |
| オンラインゲームやアプリ内課金 | 無料で提供されたゲーム内の通貨や、初回特典などを使って、ユーザーがリスクの高い行動(高額なアイテムを購入するなど)を取る場合も、ハウスマネー効果が働いています。 |
成功させるコツ
ハウスマネー効果をマーケティングで成功させるコツは、顧客に「得した」と感じさせる仕組みを作り、その感情を消費行動に結びつけることです。以下のポイントが効果的です。
1. キャッシュバックやクーポンの提供
商品購入後にキャッシュバックやクーポンを提供すると、顧客は「余分なお金を得た」と感じ、そのクーポンを使ってさらに購入しやすくなります。この心理を利用し、次の購入に繋げるように促します。
2. ボーナスや特典を付けたプロモーション
「購入すれば特典が付く」「初回購入でポイントが貯まる」など、購入者にプラスアルファの価値を感じさせる施策が有効です。顧客は「追加で得たもの」と認識し、それを使うために再び消費する可能性が高まります。
3. 割引キャンペーンの設計
期間限定で大きな割引や特典を提供し、顧客が「本来の値段より得をした」と感じさせます。得た差額分を別の商品やサービスに使おうとする行動を引き出すことができます。
4. 無料試供品やトライアル期間の提供
無料で試せる商品やサービスを提供すると、顧客は実際に購入する際に「無料で得た分を含めて、よりお得に感じる」心理が働きます。初回無料をきっかけに、リピーターを増やすことが可能です。
5. ギフトカードやポイント制度
購入ごとにポイントが貯まる、あるいはギフトカードをプレゼントすることで、顧客に「自分のお金ではなく、特別に得たもの」と感じさせ、次の消費を促します。
6. 限定オファーや特別価格の提供
特定の顧客に対して限定オファーや特別価格を提供し、「得した」と感じさせることで、そのオファーを最大限に活用しようとする行動を引き出すことができます。
7. 購入後のリマインドやフォローアップ
購入後にキャッシュバックや特典が発生する場合、その旨をリマインドして再購入を促進します。顧客がその特典を使いたくなるタイミングを逃さないことが重要です。
サンクコスト効果

回収できない労力や資金を惜しみ、今さら引き返せない、元をとらなければならない、損をしたくないという心理(埋没費用効果)。食べ放題のお店で、すでに満腹なんですが、継続して食べ続けたり、投資したお金、労力、時間などを惜しむ気持ちが、これからの意思決定に非合理的な影響を及ぼしてしまいます。サンクコスト効果を活用した方法としては、ゲームの課金があり、辞めたいけどこれまで課金した分がもったいなので継続してしまいます。
使用場面
| 購買や投資における継続的な意思決定 | すでに大きな金額を投じた商品やサービスに対して、追加投資をしたくなる場面です。たとえば、すでに修理に多額の費用をかけた車を、修理を続けることで手放さないケースが該当します。 |
| 会員制サービスの継続利用 | サブスクリプション型のサービスや会員制ジムなど、初期費用や継続的に支払っている料金が高い場合、利用頻度が低くても「これまで費やした分を無駄にしたくない」と考え、契約を続ける傾向があります。 |
| 長時間の行列や待機 | 例えば、人気のレストランやイベントで、すでに長時間待ったため「ここまで待ったからあと少し待とう」と考えて、待ち続ける状況です。 |
| 学習やキャリアの選択 | 特定の資格取得や学位取得に多くの時間と労力をかけた場合、途中で方向転換することをためらい、選んだ道を進み続けることが多いです。すでにかけた努力を無駄にしたくないという心理が働きます。 |
| ゲームやギャンブル | ゲーム内で特定のキャラクターやステージに多くの時間や資金を費やした場合、プレイヤーはそのまま続ける傾向があります。また、ギャンブルで損失を出していると「今まで失ったお金を取り返すために、さらに賭け続けよう」という行動も典型例です。 |
成功させるコツ
サンクコスト効果をマーケティングで成功させるためには、顧客が既に投じたリソース(時間、労力、費用)を意識させ、それを無駄にしたくないという心理を刺激することがポイントです。以下のコツを活用することで、この効果をマーケティング戦略に取り入れることができます。
1. 顧客の「投資」を強調する
商品やサービスに対して、既に費やした時間や努力を思い出させることで、継続使用や購入を促します。例えば、サブスクリプションモデルでは「これまでの利用データを活用して、さらにパーソナライズされた体験が得られます」とアピールすると、サンクコスト効果が働き、顧客は解約をためらうことがあります。
2. ステップ式の購入プロセスを導入する
大きな決断を必要とする商品やサービスは、段階的な導入が効果的です。初めに少額の支払いで試せるオプションを提供し、次第に本格的な購入を促すと、顧客はすでに投じた金額を無駄にしたくなくなり、最終的な購入に進みやすくなります。
3. 顧客の進捗を可視化する
ポイントカードやステータスプログラムなどで、顧客が既にどれだけ進んでいるかを示すと、目標に近づいている感覚を与え、続けて利用する動機付けが強まります。たとえば、「あと3回の来店で次のランクに昇格」などのメッセージは効果的です。
4. 特典や追加のインセンティブを提供
顧客がすでに一定の投資を行った後に、次のステップに進むことで得られる特典や割引を提示することで、投資を続けたいという気持ちを引き出します。例えば「これまでのご購入に感謝して、次回の購入が10%オフ」などが有効です。
5. 返品やキャンセルのハードルを高める
サンクコスト効果を活用するために、返品や解約の手続きを複雑にすることも一つの方法です。ただし、この戦略は顧客満足度を損なうリスクがあるため、慎重に扱う必要があります。より効果的なのは、「購入した後にどれだけ満足しているか」を強調する形で、解約の必要性を感じさせないことです。
6. 長期契約や継続プログラムの導入
顧客が長期契約を結ぶと、その後の投資を正当化したくなります。長期のサブスクリプションやメンバーシッププランを提供し、途中で解約することの「損失感」を感じさせることで、継続的な利用を促進できます。
ブレークイーブン効果

損失が生じた時、その損失分を取り戻そうとして、普段よりも積極的にリスクのある判断や行動をする心理。本来であれば、馬の状態や戦績を優先して予想するはずですが、それまでのレースで負けが込んでいると「勝ちそうにない大穴の馬に賭けて勝てば最後に損失を挽回できる」という期待感から、理屈や理論ではなく心情的に判断しリスクを負う行為のこと。
使用場面
| ギャンブルや投資商品 | ギャンブルや投資の場面で、一度損失を出した顧客が「元を取ろう」と考え、さらにリスクを取って大きな勝負に出るケースがあります。たとえば、カジノや株式投資において、損失を回復しようとして追加の資金を投入する行動が典型的なブレークイーブン効果の例です。 |
| 値引きや割引キャンペーン | 顧客が過去に高額な支払いをした商品やサービスについて、特別な値引きや割引キャンペーンを提示することで、損失を取り戻すチャンスがあるかのように感じさせる場面です。顧客は「今ならお得だ」と感じ、追加の購入を正当化する可能性があります。 |
| 返品や交換の対応 | 商品を購入した後、期待通りの結果が得られなかった顧客が、損失感を打ち消すために返品や交換を求める場面でもブレークイーブン効果が働きます。例えば、返品に対する「差額を支払えば、より高価な商品に交換できる」といったオファーが提示されると、顧客は支払いを正当化しやすくなります。 |
| 高額な支出の後の小額の追加支出 | 顧客がすでに大きな買い物をした後、少額の追加購入を提案される場面です。たとえば、高級車を購入した後、オプションのアクセサリーを追加購入することで、全体のコストを取り戻す感覚を得ることができます。この場合、追加費用を支払うことが「価値がある」と判断されやすくなります。 |
成功させるコツ
ブレークイーブン効果をマーケティングで成功させるためのコツは、顧客の「損失を取り戻したい」という心理をうまく刺激し、購買行動を促すことにあります。以下のポイントを考慮すると効果的です。
1. 追加の価値を強調する
顧客が過去に高額な支出をしている場合、その価値をさらに引き上げる追加商品やサービスを提案することが重要です。たとえば、「このオプションを追加すると、さらにお得感が増す」とアピールすることで、追加購入を促すことができます。
2. キャンペーンや割引の活用
期間限定の割引や「今なら〇〇円お得」といったキャンペーンは、顧客が損失を取り戻すチャンスがあると感じさせます。特に、すでに大きな買い物をした顧客に対して、タイミングを見計らって値引きを提供することで、追加購入を誘発できます。
3. 損失感の演出
「今この商品を手に入れないと損をする」といった、購入しないことによる損失を強調する戦略も有効です。たとえば、在庫が少ないことや価格が上昇する可能性があることを伝えることで、顧客が行動を起こしやすくなります。
4. リスクの軽減を訴える
顧客が再度リスクを負うことに対して不安を感じる場合、そのリスクを軽減する保証や返金制度を提供することが有効です。これにより、顧客は「損失を取り戻せる」と感じやすくなり、購買を決断する可能性が高まります。
5. 購入履歴に基づく提案
すでに大きな支出をしている顧客に対して、購入履歴に基づいたパーソナライズドな提案を行うことで、損失を取り戻す感覚を提供します。過去の購入と関連性の高い商品やサービスを提案すると、顧客は自然に興味を持ちやすくなります。
スネークバイト効果

損失が発生した際「今後さらに損失が膨らんでしまうのでは」と恐れ、それ以降リスクを避けるようになる行動心理。買ったのは良いがすぐに損失が出てしまう。しかし、中々損切ができなくて気が付けば半分以下に。最後はしぶしぶ全て売却して「もう投資は一切しない」と投資を辞めてしまい、トラウマ状態になります。
使用場面
| 再購入を躊躇する顧客へのアプローチ | 過去にそのブランドや類似商品で失敗や損失を経験した顧客は、再度の購入に対して非常に慎重になります。例えば、以前に高価な商品を購入して効果が感じられなかった顧客が、その経験によりリスク回避的になる場面です。 |
| 新商品や新サービスに対する消極的な態度 | 新しいものを試すこと自体にリスクを感じる顧客が、過去の経験から新商品や新サービスを避けることがあります。これは、特に高額商品や、長期的な契約が必要なサービスの場合に顕著です。 |
| リピートビジネスにおける課題 | 一度でもネガティブな経験をした顧客は、その企業やブランドと再び取引することに抵抗を示します。特に、前回の取引が期待外れに終わった場合、顧客が再びリスクを取りたくないと感じることが一般的です。 |
| 金融や投資におけるリスク回避 | 投資や金融商品を扱う場合、顧客が過去に損失を被った経験から、再びリスクを取ることを避けることがあります。特に、投資で大きな損失を経験した顧客は、より安全志向の選択を取る傾向が強まります。 |
| 高額商品やサービスの購入時 | 高価な商品の購入に失敗した経験を持つ顧客は、次回の購入に対して非常に慎重になり、同じような商品を避けようとする場合が多いです。このような状況では、安心感やリスク軽減を強調する必要があります。 |
成功させるコツ
スネークバイト効果をマーケティングで成功させるためには、過去のネガティブな経験を持つ顧客に対して、リスクを軽減し信頼を回復させる戦略が重要です。以下のコツが効果的です。
1. 保証や返金制度を明確にする
過去に失敗や損失を経験した顧客はリスク回避的になるため、安心感を与えることが鍵です。購入後の返金保証や、商品・サービスの保証期間を強調することで、リスクを最小限に感じさせ、再挑戦を促します。
2. 顧客の不安を解消する具体的な証拠を提示
実績、顧客レビュー、信頼性を裏付けるデータなどを提供することで、製品やサービスの改善点や、過去のネガティブな経験が解決されたことを示します。これは特に、リピーター獲得に有効です。
3. トライアルやサンプル提供
小さなリスクから始める機会を提供することで、顧客が過去の失敗の影響を少なく感じるようにします。試用版やトライアル期間の提供は、顧客に自信を持ってもらい、再び試してもらうきっかけになります。
4. 個別対応で顧客の信頼を回復
パーソナライズされたアプローチや、顧客との対話を通じて不安を取り除くことで、過去のネガティブな印象を払拭します。例えば、サポートの充実やカスタマーサービスの強化を図ることで、顧客に対してケアを示すことが重要です。
5. 改善点のアピール
過去の失敗を踏まえて、どの部分が改善されたのかを顧客に明確に伝えることが重要です。「以前の問題点を解決しました」というメッセージを積極的に伝えることで、リスク軽減をアピールします。
6. 価格の見直しや割引の提供
顧客が失敗を恐れている場合、価格面でのリスクを低くするための割引やプロモーションが有効です。特に、過去の購入者には特別なオファーを提供することで、再挑戦しやすい環境を作ります。
7. 小さな成功体験を提供
小さな成功体験を積ませることで、顧客の自信を回復させ、次の購入に繋げます。例えば、簡単な手続きや少額の商品を薦め、成功体験を重ねることで、顧客が再び大きな決断をする準備を整えます。
お知らせ
CEVSTYでは、スタッフが撮影したり編集ができるための研修サービスを用意しています。スタッフが広報力を身につけることで、訴求力のある情報を発信することができ、良好なイメージを構築・維持することができるようになります。
現在提供しているサービスについては、企業の状況に合わせてオーダーメイドで研修を組み立てるため、年間でのご契約に限りがございます。ご興味があるご担当者様は取り急ぎ、お問い合わせ等をしていただけると幸いです。

