これからのビジネスに必須な人材
クリエイティブマーケター
こちらの記事をご覧いただいている方は、初めて広報担当になった方、採用や集客で悩むオーナーさん、これから開業を考えているフリーランスの方だと思います。クリエイティブマーケターになるためには、マーケティングについての基本的な流れや考え方を理解しておく必要があります。今回紹介する内容を把握していれば大丈夫です。
レッスン内容
マーケティングとは
ドラッカー氏は「マーケティングの理想は、販売を不要にするものである」と述べています。お客様に「買ってください!」とプッシュしなくても、お客様から自然に買いたくなる状態をつくることであり、お客様のニーズに合った商品を、適切なターゲットに向けて発信していくことが理想です。そのために、商品開発から販売戦略の策定、広告宣伝に効果検証まで、一連のプロセスを一貫して計画して実行・管理する必要があります。つまり、マーケティングとは「商品が売れる仕組み」をつくることです。
具体的なプロセス
集客・販売・採用を成功させているマーケターが実施している6つの基本的なプロセスになります。
| プロセス | 概要 |
|---|---|
| 市場分析 | 市場や競合他社の動向などのデータを収集し、自社の強みや取り巻く環境を整理する。 |
| セグメンテーション | 市場分析に基づいて市場を細分化し、属性やニーズなどの共通点を持ったグループに分けていく。 |
| ターゲティング | 市場グループの中から、自社の商品が最も販売できそうなターゲットを選別していく。 |
| ポジショニング | ターゲットにおける自社の立ち位置を決定し、競合他社と差別化するコンテンツを開発する。 |
| プロモーション | 開発した新商品の認知を拡大するために、広告宣伝に関する戦略を設計する。 |
| ブランディング | ファンを増やすめに、キャンペーンやイベントなど企画して実施していく。 |
市場調査について
市場調査とは「数字や数値で現在の市場を把握し、マーケティング施策(どうすれば製品が売れるかの作戦)を立てること」を指します。例えば、新しい車を開発しようとしていたとします。売るためには、顧客のニーズを把握して製品を作らねばなりません。市場調査では、そのために知っておくべき情報を収集し、分析し、製品開発に役立てます。例としては、以下のようなことを調べます。

- 国民の車の所有率
- 一人当たりの所有台数
- 一台にかける価格
- 購入してからの買い替え年数
- 購入で重要視する部分
- 販売メーカーの数
- メーカーの史上占有率
|市場調査の代表的な3つの方法
| 定量調査 | 消費者や見込顧客に対して、対面・郵送・Webなどを用いてインタビューやアンケートを行い、データを収集します。市場調査の最も代表的な方法といえます。よく使われているのがインターネット調査で、インターネットを通じてアンケート回答を依頼します。メリットは、インターネット上で行うため回答者の負担が少なく、他の調査と比べて低コスト・短期間で多数のサンプルを集めて調査できることです。文字だけでなく、画像や写真・動画を使って調査することもできます。デメリットは、高齢者などネットを利用しにくい世代の回答を得ることが難しい、商品やサービスと回答者の関係性が低い場合は回答の信頼性が低くなる、機密性の高い情報の調査は難しいことなどがあります。 |
| 定性調査 | 属性(年齢・性別・職業など)が共通するグループにグループインタビューを行い、顧客の本音や本人が認識できなかった意見を引き出す手法です。具体的には、4~6人の調査参加者に集まってもらい、モデレーターと呼ばれる進行役がインタビューを行います。メリットは、アンケートではわかりにくいユーザーの意見や感想など定性的な情報を得られることです。回答者の返答によってその場で質問を変えることもできます。デメリットは、会場設定や参加者を集めるための時間と費用が発生します。また、影響力の大きい参加者がいた場合、その他の参加者の考え方が左右される可能性があります。 |
| 統計データ調査 | 政府や大学など公的機関が調査・公表している統計データをもとに、ターゲットとなる顧客の属性(年齢・性別・職業など)に合わせて、数値の割り出しや統計データを調査します。デスクリサーチとも呼ばれ、Webサイトや社内にある既存の資料を使ってデータをもとにリサーチすることもできます。調べたいテーマの市場や業界動向を調べる場合に適しており、「調査したいキーワードでネット検索」「Webで既存資料・統計を収集する」などの方法が一般的です。メリットは、時間をかけずに幅広く情報を集めることができること。デメリットは、情報の真偽性が不明であったり、著作権の制限があったりした場合はデータが活用できないことです。 |
セグメンテーションについて
セグメンテーションとは、市場を様々な切り口で分類し、特定の属性ごとにグループ(セグメント)化することです。細分化した市場の一部をターゲットとして戦略的に投資することで、競合他社に対して優位性を築き、自社製品やサービスの販売拡大や占有率を高めることができます。

セグメンテーションを行う場合に、思いつくままに市場を細分化するだけでは意味がありません。自社のターゲットとして最適な層を選択するためにマーケターが活用している「4R」の判断基準をご紹介します。
| Rnak(優先順位) | 1つ目のRは「Rank(優先順位)」です。各セグメントの特徴を自社の経営戦略と照らし合わせ、重要度によって優先順位をつけます。 |
| Realistic(規模の有効性) | 2つ目のRは「Realistic(規模の有効性)」です。対象となるセグメントに、十分な売上や利益を確保できる規模があるかを調べます。 |
| Reach(到達可能性) | 3つ目のRは「Reach(到達可能性)」です。対象となるセグメントに対して、プロモーションや商品、サービスを実際に届けることができるかを調べます。 |
| Response(測定可能性) | 4つ目のRは「Response(測定可能性)」です。セグメントの規模や購買力、特性などを明確に測定できるか、マーケティング後の反応を測定できるかを確認しておきます。 |
|市場を細分化する糸口
| 1)属性に関するデータ | 年齢・性別・職業・所得・学歴・家族構成・世帯規模など、人の変わらない基本情報を基にしたセグメント指標です。統計調査などを基に判断します。 |
| 2)心理に基づくデータ | 価値観・性格・ライフスタイル・購入動機、などといった個人の心理に基づく情報を使ったセグメント指標です。アンケート調査やヒアリングなどを行った結果を基に判断します。 |
| 3)行動パターンによるデータ | 買い物の頻度・買い替えのタイミング・使用用途などといった個人の行動に焦点を当てた情報を使ったセグメント指標です。ユーザーの行動追跡データなどを基に判断します。 |
| 4)地理的な要因に関連するデータ | 国・市町村・気候・文化・宗教など、地理的要因に絡む情報を基にしたセグメント指標です。地図や国の調査結果などを参考に判断します。 |
ターゲティングについて
ターゲティングとは、セグメンテーションによって細分化された市場の中から、自社がターゲットに据える市場を選ぶプロセスのことです。市場には多種多様な顧客層が存在しているおり、競合も存在しています。ターゲティングを通じて市場を絞り込めば、特定の顧客が抱えるニーズに応える製品を提供するための戦略策定につながります。このとき、自社が勝負するのに適した市場を選ぶことができると、事業の戦略を明確化することができます。

市場を定めるポイントは、細分化した市場の中で、「今後の成長が期待でき、かつ競合企業も少なく、顧客企業のニーズが見込まれる」部分を見つけ出すことです。市場調査をして、どの市場を攻略するのかを決定する前に、下記の6項目を必ず再チェックしておきましょう。
| 1)潜在顧客はいるのか? | 市場規模がビジネスとして成り立つだけの潜在顧客がいるかどうか。一般的には規模が大きい方がビジネス拡大のチャンスもありますが、その分ライバル企業も多くなります。 |
| 2)商品へのニーズがあるのか? | ターゲットとなる顧客企業が自社の商品・サービスに関心を持ち、優先して手に取ろうとしてくれるのか、という観点。 |
| 3)競合他社どれだけある? | 市場にどれぐらいの競合他社にいるのか、という観点。競合が多ければ多いほど自社の商品・サービスが目に留まりにくい。市場規模うや成長率とも関係性のある項目。 |
| 4)顧客はまだ増えそうか? | 市場がどれだけ成長しているのか、という観点。成長期で認知度も上がっている市場は、最も事業参入がしやすい時期であるとされる。 |
| 5)認知させれるのか? | ターゲットとなる顧客に対して自社の商品・サービスを提供する上で、商品やサービスについて認知してもらうことができるかどうか。物理的距離やネット環境下にある否か等が関係する。 |
| 6)顧客の反応は確認できるのか? | 販促の効果を測定できるのか、という観点。顧客からの反応を調べることで、次への戦略を立てることができます。顧客からの反応が把握できるかどうか。 |
|ターゲットを絞る目安
| 無差別型 | セグメントされた市場間の違いを無視して、同じ商品をすべての市場に供給する手法です。一般的に大企業に多い手法で、食料品などが該当します。 |
| 差別型 | 複数のセグメントされた市場に、それぞれのニーズにあった商品やサービスを提供する手法です。複数の料金タイプの設定、似たジャンルの商品を機能を変えて販売するなど、多くの企業で採用されています。 |
| 集中型 | 1つ、もしくはごく限られた市場に集中してマーケティングを行う手法です。高級メーカーやニッチな商材を販売しているなど、コアなファンを抱える企業によく見られるパターンです。 |
ポジショニングについて
ポジショニングとは、ターゲット市場において、自社が他社よりも優位に立てる位置付けを見出すことです。自社がとったポジショニングは市場に認知され始めて意味をなします。ポジショニングを行う上で大切なのことは、競合と比較する軸を持つこと。値段や、品質、店舗数、販売チャネルなど、多くの指標の中から必要なものを選び、競合と比較します。

ニーズのある市場でも、例えばすでに大手が進出している場合は、一般的にはそこで大きな利益を出すことは難しい傾向にあります。しかし、すでに進出している大手にはない要素で差別化できれば、レッドオーシャンでも利益を得られる場合もあるでしょう。ポジショニングに設定する前に、3つのポイントをチェックするようにしてください。
| 1)顧客のニーズを満たすものか | 他社を意識しすぎて差別化したポジション設定にニーズがなければ失敗する可能性が高くなります。ポジショニングマップを活用する際も、顧客が商品を決定する上で重要視する要素を軸にした上で、需要の有無や大きさについても必ず意識しておきましょう。 |
| 2)自社の理念や戦略との整合性 | 高級品としてブランディングされているのにも関わらず、価格設定を低くするポジショニングは、会社の理念や製品との一貫性がなくなってしまいます。そのため、ブランドイメージを損ねたり、既存客の失う可能性があります。差別化や顧客ニーズも大切ですが、自社の理念や戦略も考慮しておきましょう。 |
| 3)相関性が低い軸を設定する | ポジショニングマップで、「価格」と「性能」を軸にしてしまうと、相関性が高くなるため、軸として適切ではありません。価格が高くなるにつれて性能が良くなることは当然だからです。 |
|ポジショニングの手順
| 1)縦と横の2つの軸を決める | 1つ目の軸は、顧客に対して自社が持つ競争優位点を訴求できるポイントを複数リストアップします。2つ目の軸は、競合と差別化できるポイントをリストアップします。競合に対して優位性が高くても、顧客のニーズに照らし合わせることを忘れないようにしてください。その際、2つの軸が相関関係でないように設定することが重要です。 料理の種類 価格 料理の量や大きさ 特別な食材 お店の場所 店内のレイアウト 客層の年齢や属性 |
| 2)他社のポジションを配置する | 2つの軸を設定したら、ターゲット市場でライバルとしてピックアップした競合店を配置していきます。直接的なライバルだけでなく、大手やチェーン店なども配置することで、分布図の精度を上げていきましょう。 |
| 3)自社のポジションを配置する | これからの市場で有利になれるポジションを検討していきます。マップ上で空白になっている箇所は、競合他社が着手していない領域なので、差別化しやすくなり、独自の価値を提供しやすくなります。 |
プロモーションについて
顧客の設定とベネフィットがまとまったら、メイン顧客に向けて認知拡大をするプロモーション戦略を組み立てていきます。皆さんは新商品をどのようにして知りましたか?テレビCM、YouTube、SNSなどのように顧客が認知する方法は多様化しています。
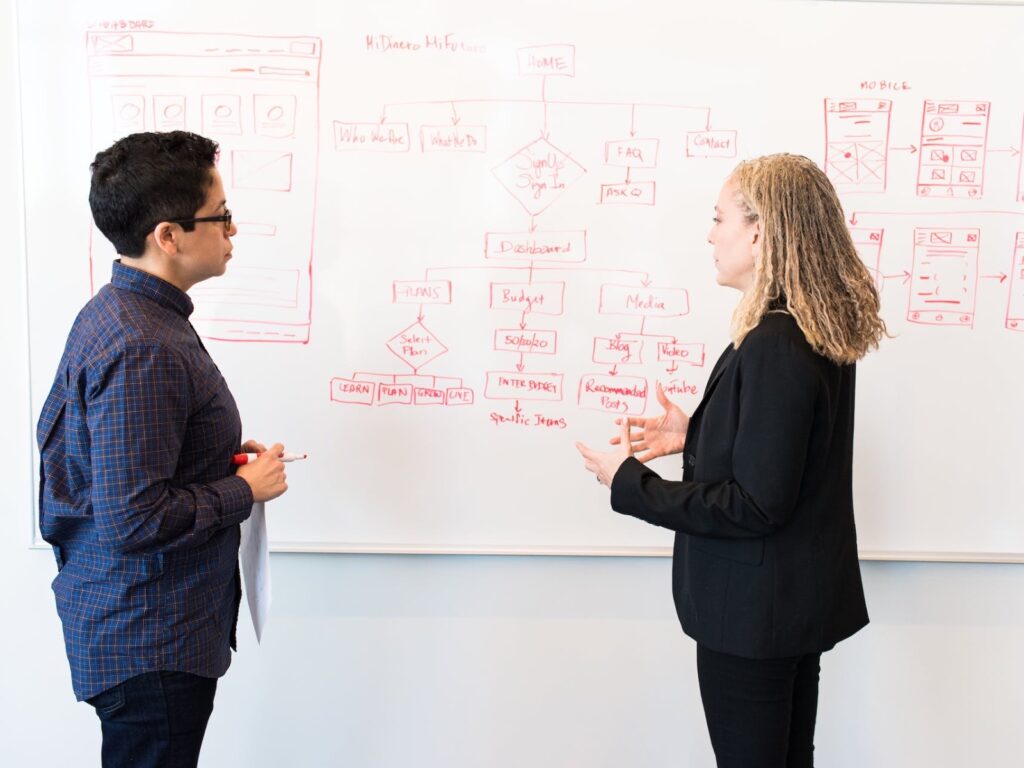
- チラシやダイレクトメールを送る
- メールマガジンを配信する
- 広告を掲載する
- セールやキャンペーンを実施する
- 商品の試供品を配布する
- 会員サービスやポイントサービスを用意する
近年の広告は、主にオンライン広告とオフライン広告の二つに分けることができます。オンライン広告はWeb上にある広告で、リスティング広告やディスプレイ広告、SNS広告などになります。オフライン広告とは、テレビや雑誌、ラジオや看板などになります。
| 項目 | メリット |
|---|---|
| オンライン広告 | ・手軽に始められる ・効果測定が可能 ・ターゲットにピンポイント |
| オフライン広告 | ・露出が保証される ・エリアのターゲットしやすい |
|オンライン広告の種類と特徴
| 純広告 | Yahoo!のように大手ポータブルサイトなどをはじめ、サイトの枠を買い取る形で掲載される広告のことです。純広告は費用が高額になる傾向がありますが、ターゲット層にマッチしたメデイアを選択できれば、多くの人にリーチ(見てもらえる)される可能性が高くなります。 |
| タイアップ広告 | タイアップ広告とは、自社以外の誰かと出稿される広告です。芸能人やYouTuberなどの著名人から大手ポータルサイトなどのメディアの場合もあります。漫画や映画などの企業がコラボするケースもあります。 |
| 動画広告 | 動画広告で多いのはインストリーム広告です。YouTubeなどの動画再生前に表示される広告です。動画広告やSNS以外の外部メディアに配信するタイプの動画広告はアウトストリーム配信広告と呼ばれます。 |
| ネイティブ広告 | SNSやニュースサイトなどのフィードに溶け込むような形で表示される広告です。テキストや画像はもちろん、動画を活用した広告もできるサービスが増えています。 |
| SNS広告 | SNS広告はTwitterやInstagramなどのSNS上で配信される広告です。SNS広告にも種類があります。SNS運用企業が保有するユーザーの属性や行動履歴のデーターを活用して、狙った相手にピンポイントにアプローチすることができます。 |
| リスティング広告 | GoogleやYahoo!などの検索エンジンの結果一覧ページに表示される広告です。ユーザーの検索ワードに連動して広告を出すことができるので、見込み度の高いターゲットにアプローチすることができます。リスティング広告は予算を見積もりしやすく、測定しやすいのが特徴です。 |
ブランディングについて
「ブランド」とは、類似した商品から区別するために差別化したものです。商品のデザインやシンボルマーク、ブランドロゴ、商標、名称、キャッチフレーズ、記号など、様々な要素が組み合わさってブランドを形作ります。そして、そのような「ブランド」を消費者に認知させ、自社(製品、商品)の強み・ポジションを明確化して、ファンを増やすことが「ブランディング」活動です。

例えば、久しぶりに会う大事な友人と食事をする際に、「景色が綺麗」「おしゃれで可愛い」お店を探したり思い浮かべたりします。そのイメージは、自分が実際に利用したり、何かのメディアで見たり、友人から聞いた話かもしれません。そのようなお店に対するイメージがブランディングになります。
|ブランディングへのステップ
| ブランドコンセプト | ブランディングをすることで、強いイメージを植え付けることになります。どのような印象を持ってもらいたいのか「コンセプト」を決める必要があります。その「コンセプト」に準じたロゴ・商品名などを設定することで、一貫性が生まれるため、消費者にとってもシンプルでわかりやすく認識されます。 |
| ブランド価値 | ブランド価値を設定することで、競合他社との差別化やブランド力の向上につなげることができます。顧客に対して何を価値としてイメージ化させたいのか決めておきましょう。 実利価値・・・品質、機能、使いやすさ 感性価値・・・デザイン、ブランドの個性 情緒価値・・・好印象の使用実感や体験 共鳴価値・・・価値観の表現、社会的実現 |
| タッチポイント | タッチポイントとは、顧客とブランドとの接点になります。どのようなきっかけでブランドを知ってもらうのか?商品やサービスの認知だけでなく、商品やサービスのイメージを強調させることが重要になります。 イベント キャンペーン インタビュー インフルエンサー |
マーケティングの歴史
マーケティングは19世紀のアメリカで生まれた概念です。不良在庫を抱えずに経営をスムーズに行うにはどうしたらいいのか、効率的に販売する方法を探したことが始まりだと言われています。近年のテクノロジーの進歩や人々のライフスタイルの変化によって、マーケティングの手法やデザインも進化してきました。過去から現在のマーケティングについて確認していきましょう。
- |マスメディアの広告
-
マスメディアとは、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌など、不特定多数の人々に対して情報を発信する媒体のことです。人々は、広告や情報番組によって新商品やサービスのことを認知して購入していました。ドラマや芸能人が身につけているものが流行して、社会現象になることもしばしば発生しました。

- |インターネットの広告
-
情報に関してはテレビや新聞は見ずにインターネットを利用する人が増えていきます。楽天やamazonが登場し、最初は商品を見ないと買えないなどの抵抗感もありましたが、店頭よりも価格が安く、指定した住所まで届けてくれるなど、安心であることが判明したことで、ネットショップを利用する人が増えました。ネットで購入する際に登録したメールで広告配信する手法が増え、性別や年齢など、属性に合わせたアプローチが可能になっていきました。

- |ブログによる認知の拡大
-
一般人が情報発信を始めて、影響を与えることができるようになったのはブログです。無料で文章や画像をアップすることができ、芸能人も参入していきました。この頃からブログが広告媒体として価値があると判断され、企業側がブロガーに依頼する企業案件が登場しました。ブログで紹介される商品が売れていくため、アフェリエイトと呼ばれる広告収入のビジネスモデルが流行していきます。

- |検索エンジンの活用
-
“ググる“という言葉ができ、Webで商品について検索する機会が増えるため、キーワードで上位に表示されることで、ホームページを閲覧されることになり、Google検索の上位に表示されることが認知拡大の媒体として活用されるようになります。この頃から検索表示に関するSEO対策が研究され、ホームページのデザインを強化するWebマーケティングが発展していきます。

- |スマートフォンの登場
-
2006年に最初のiPhoneが登場し、さらに個人と個人が手軽につながるSNSとしてfacebookが登場します。実名を出すことで、信頼感を得ることができ、連絡先を知らない人でもつながることができるようになりました。個人同士でつながることに警戒しなくなり、Twitter、InstagramなどのSNSが開始したことで、情報取集の流れが大きく変わりました。

- |4Gによる通信速度の変化
-
2010年ごろに3Gから4Gへと通信システムが進歩したことで、短時間で大量のデータを転送することが可能になりました。この頃から注目され始めたのがYouTubeになります。購入した商品の投稿がブログと同じように消費者が参考にするコンテンツとなり、美容、ガジェットなどのジャンルができるほどに進化していきました。

- |インフルエンサーの登場
-
通信速度の向上、デバイスの進化、アプリの開発によって、SNSやYouTubeのクオリティが飛躍的にアップし、SNSで検索する人々が増加。チャンネル登録、いいね、フォローなどの言葉が生まれました。ただ、視聴する側としては迫力があったり、他で見ることができないため、登録すファンが増え、広告として活用できるSNSマーケティングが登場しました。SNSで登録者が多い人をインフルエンサーと呼び、そのSNSで紹介された商品が売れる流れを作り出しました。

- |ステルスマーケティングが横行
-
実際には使用していないのに、まるで愛用者として紹介するステルスマーケティングも問題視されました。ステルマだとバレると、そのアカウントは嫌煙されるため、企業案件で商品を紹介する場合は、プロモーションを含みますと画面に表示されていることが多くなりました

- |ショート動画の到来
-
その後もTiktokによる動画が若者から流行りましたが、数年後には広告としての活用されており、ビジネスアカウントも用意されています。これまでの歴史を振り返ると、ブログなどの文字からインスタグラムの画像、そしてYouTubeの映像にシフトしていることや、文字数が多かったブログが140文字のツイッターのように短くなり、動画もTikTokのようにショート版になったことです。

- |多様化した広告媒体
-
情報の入手方法が、文字、画像、映像を選択でき、媒体もテレビ、ネット、SNSなど多様化しているため、企業側はマーケティング戦略をしっかりと構築して、常に進化していく必要があります。さて、ここまでマーケティングの歴史についてお話しをさせて頂きました。10代の一般人から流行し、企業と芸能人が参入する歴史が繰り返されていることを確認できたと思います。

- |これからのマーケティングスタイル
-
マーケティングを強化するためにWebやSNSを活用すると思いますが、すべての商品やサービスで効果が出るわけではありません。デジタルマーケティングは対面と異なり一方通行になるため、ターゲットを絞って訴求効果を上げる必要があります。

代表的なマーケティングモデル
19世紀から生まれた概念であるマーケティングは様々なモデルを生み出してきました。現在も使用されている一般的なマーケティングモデルの特徴をご紹介します。
| マスマーケティング | 不特定多数の消費者に対し、統一的・画一的なプロモーションを行うマーケティングのことです。インターネットが普及した現在も大規模で実施されており、テレビCMや新聞・雑誌広告などが代表例です。食品・飲料・日用雑貨品・化粧品・車・保険といった製品・サービスの多くで、マスマーケティングが行われています。消費者にも身近なマーケティング手法と言えます。多数の消費者をターゲットとする以上、多くのコストがかかるため、大企業が実践しやすい手法です。 |
| ダイレクトマーケティング | ターゲットとする顧客を定め、双方向のコミュニケーションによって販売促進を展開するマーケティング手法です。通信販売、通信教育、ECなどで利用されるケースが多く見られます。顧客の反応を分析することにより、効果検証がしやすいメリットもあります。IT・通信環境の進化によって、さらに活用できる場が広まっています。メールやSNSを利用して双方向性のコミュニケーションを展開する手法も、ダイレクトマーケティングの1つです。 |
| ステルスマーケティング | ステルスマーケティングとは、宣伝と気づかれないように、製品やサービスを宣伝する行為のことです。映画やドラマで女優が使用していた服やアクセサリーなどでよく活用されています。一方でインフルエンサーに依頼をして、あたかも商品のファンであるかのように投稿することで、ユーザーを欺く行為に見えるため、企業や商品のイメージを落とす場合があるので注意が必要です。 |
デジタルマーケティングの種類
あらゆるデジタル関連のツールやサービスを活用するマーケティングです。Webサイト、検索エンジン、スマホアプリ、動画配信、SNS、Eメール、VR、IOT、デジタルサイネージなど多岐にわたります。デジタルを介して顧客との接点をつくり、関係を構築していき、最終的には製品・サービスの利用につなげます。
| Webマーケティング | デジタルマーケティングのうち、Webに特化したマーケティングのことです。アクセス数やWeb上での顧客の動きなどを測定・分析し、集客数の増加や製品・サービスの問い合わせ・申し込みにつなげます。Webマーケティングの代表例がSEO(Search Engine Optimization)で、検索エンジン最適化のことを意味します。Google検索で、自社のサイト・ランディングページが上位になることを目指す手法です。 |
| コンテンツマーケティング | ユーザーにとって役に立つコンテンツを提供することにより、自社のファンとなってもらい、申し込み・購入につなげる手法です。潜在顧客に適切な情報を提供することで引き付け、徐々に購入を促していきます。コンテンツとは「情報の内容・中身」を意味するので、利用するメディアは特に決められていません。例えば、英語の教材を販売したい場合に、有料級のコンテンツを登録者に提供して価値を感じてもらう方法などがあります。 |
| SNSマーケティング | Instagramなどのソーシャルメディアを活用するマーケティングです。SNSの特性である双方向のコミュニケーションを図ることで、若年層を中心としたファンを増やせるのがメリットです。公式ホームページとは違い、カジュアルで親しみやすいメッセージを投稿できるのもSNSのメリット。シャープ、タニタ、ローソンなどの企業アカウントは個性的なことで有名です。SNSで大きな影響力を持つ個人に協力してもらい、自社商品の写真の投稿やアピールなどをしてもらうことを、「インフルエンサーマーケティング」と呼びます。 |
| 動画マーケティング | 映像を利用して、商品やサービスの魅力を訴求するマーケティングです。YouTubeなどの発達により、中小企業や個人事業者でも動画マーケティングが実践できるようになりました。動画は視覚や音声により一度に伝達できる情報量が多く、わかりやすく伝えられるのがメリットです。動画広告の市場規模も年々拡大しており、現在注目されている手法と言えます。 |
成功させる4つのポイント
デジタルマーケティングは、情報が一方通行なので、顧客の話を聞いてから提案を変更するなどの臨機応変な対応ができません。そのため、ある程度顧客像を絞り込んで、その顧客だけに訴求できるコンテンツや広告が必要になります。デジタルマーケティングで成功させるための4つのポイントをご紹介します。
- |1、一人ひとりの顧客に合わせた施策
-
デジタルマーケティングであるWebやSNSは、一人ひとりの顧客に合わせた施策を立てて実行することが可能です。 中でも顧客と直接やり取りそを行うD2Cのビジネスモデルが増えています。販売業者を介さないことで、自社の収益性を高めるだけでなく、売り方も自由に設定することができます。さらに顧客のデータも取得できるため、今後のマーケティング戦略の分析に役立たせることができます。
- |2、顧客データを蓄積して活用
-
顧客データを日々蓄積・管理して分析すれば、個別の施策を考える際に活用でき、なおかつ自社の顧客全体の傾向を把握することもできます。今後の新たな集客や顧客獲得のためにも役立てられるでしょう。 ホームページやSNSには、顧客がどのような経路でサイトにアクセスしたのか、検索ワードは何か、などを無料で分析できるツールが用意されています。定量データだけではなく、アンケート機能なども活用することで、商品の色や形などについてフォロワーにヒアリングすることも可能です。
- |3、顧客へのフォロー体制
-
顧客に対するアフターフォローも欠かせません。ユーザーサポートはもちろんですが、自社の商品・サービスに関する継続的な情報提供を行えば、次の購入に結びつける有効なマーケティング方法となります。 具体的には、サポートセンターの設置、メール、チャット、SNSを介した問い合わせ対応、オウンドメディア内のコンテンツによる情報発信などが挙げられます。顧客へのフォローが万全であれば顧客ロイヤルティが高まり、「顧客のファン化」にも結びつけることが可能です。
- |4、マーケティングツールを活用する
-
販売データや顧客データを管理し、分析するための各種マーケティングツールも高機能化・多様化しています。代表的なツールとしては、SFA(営業支援)やCRM(顧客管理)、MA(マーケティングオートメーション)などがあります。また、ウェブアクセス解析ツール、分析に役立つBIツールなども、多くの企業が導入しているツールです。 これらのツールを活用すれば、必要な情報をいつでも参照し、リアルタイムに近い早さで分析結果を得ることも可能です。現在のマーケティングでは、データをいかに有効に活用するか、その正確性とスピードが非常に重要なものとなっています。
まとめ
マーケティングの基礎知識はこれで理解できたと思います。SNSやYouTubeを活用したマーケティング方法も紹介しています。これからの時代は、動画制作と発信力のスキルを身につけておくことで、活躍の幅も広がります。一通りの知識をつけたら、SNSなど自分たちができる範囲からスタートさせましょう。すでに始めている場合は、もう一度顧客の設定と投稿内容の見直したり、フォロワー数やいいね数が多い投稿をオマージュしたりイミテーションして下さい。CEVSTYでは、マーケティングで役立つ情報も発信していきます。
無料会員登録すると
すべてのコンテンツが見放題












