これからのビジネスに必須な人材
クリエイティブマーケター
インターンシップの種類と定義
経団連と大学の関係者でつくる採用の在り方を議論する協議会が開かれました。そこでまとまった報告書では「インターンシップについて一定期間、学生が実際に職業を体験することなどを条件に、企業の採用活動に活用できるようにすべき」とされています。
これにより、インターンシップで得た個人情報を採用活動に使用することができるようになりました。しかし、すべてのインターンシップが対象ではありません。
インターンシップの種類と定義
インターンシップには4つのカテゴリーに分類されています。
| タイプ | 実施期間 | 就業体験 | 担当社員 | 情報利用 |
|---|---|---|---|---|
| オープン・カンパニー | 1日 | なし | 任意 | × |
| キャリア教育 | 1〜3日間 | 任意 | 任意 | × |
| 専門活用型 | 短期 5日間以上 長期 2週間以上 | あり | 現場の社員 | ◯ |
| 高度専門型 | 2ヶ月以上 | あり | 現場の社員 | ◯ |
- ◼️ オープン・カンパニー
-
1日限定で実施されるものは「オープン・カンパニー」というタイプに分類され「インターンシップには該当しない」と定義されました。あくまで企業や仕事を知る機会だとして、採用活動に使うことは認められていません。
- ◼️ キャリア教育
-
次の「キャリア教育」という分類。「オープンカンパニー」より長い期間で実施されるものの、あくまでも参加者の教育が目的で就業体験は「任意」。こちらもインターンとはみなされず、採用には使えません。
- ◼️ 汎用型能力・専門活用型
-
一般的なプログラムなら最低でも5日間以上、専門性を重視するなら2週間以上の期間実施されるものが対象です。そして、こちらでは「就業体験」が必ず行われます。就業体験は実施期間のうち半分を超える日数、職場で行うとしていて、事務所や工場、研究所などに学生が同行して体験することが必要です。ただし、テレワークを日常的に使っている企業ならテレワークも可としています。
就業体験の際は人事担当者ではなく「その職場の社員が学生を指導し、インターンシップ終了後にフィードバック」すること。そして「学業との両立に配慮する」ことを理由に対象は学部3・4年生か修士1・2年生。期間は夏休みや冬休みなどの長期休暇に行うこととしています。
- 最低5日間以上
- 就業体験が必須
- 実施期間の半分以上で就業体験
- 現場社員の対応とフィードバック
- 長期休暇の期間に実施
- ◼️ 高度専門型
-
高度専門型インターンシップは大学院生を対象とした、より専門的なインターンシップを想定しているそう。採用に活用するための条件は基本的に上記と同じです。
学生たちの意識調査
2025年卒から本格始動する採用直結型インターンシップにより、各社が学生にアンケートを実施しています。それぞれのデータをご覧になって傾向をチェックしてください。
学生がインターンに参加する理由
学生がインターンシップに参加する理由や背景には、以下のような点があります。
| 実務経験の取得 | 学生は、実際の仕事環境での経験を積むことで、将来のキャリアに役立つスキルや知識を得たいと考えます。これは、特に就職活動の際に重要視されるポイントです。 |
| ネットワーキング | インターンシップを通じて業界のプロフェッショナルと知り合うことができ、人脈を広げる機会を得ます。これにより、就職先の選択肢が増えることも期待されます。 |
| キャリアパスの確認 | 自分が興味を持つ分野で実際に働いてみることで、その分野が自分に適しているかどうかを確認することができます。また、異なる業界や職種を経験することで、将来のキャリアパスを具体的に描く手助けになります。 |
| 履歴書の強化 | インターンシップの経験は、履歴書に記載することで他の応募者と差別化を図る要素になります。特に新卒の場合、実務経験が少ないため、インターンシップは貴重なアピールポイントとなります。 |
| 大学のカリキュラムの一環 | 一部の大学では、インターンシップが単位取得の条件となっていることがあります。学生はこの要件を満たすためにインターンシップに参加します。 |
| 実践的なスキルの習得 | 学校で学ぶ理論的な知識だけでなく、実践的なスキルを身に付けるためにインターンシップを活用します。これにより、即戦力としての能力が高まります。 |
| 自己成長と自信の向上 | 実際の職場での経験を通じて自己成長を感じ、自信をつけることができます。問題解決能力やコミュニケーション能力など、ソフトスキルも向上します。 |
人気があるインターンシップ
インターン企画は年々増加しており、中にはユーモアのある内容で人気を集めている企業もあります。国内企業のインターンシップの情報をランキング形式で紹介している「みん就」によると、下記のような内容がランキング上位になっているようです。みん就のホームページはこちら>
| 題名 | 時期 | 期間 | 場所 | テーマ | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品開発 | 8月上旬 | 1日 | 大阪 | ニトリについて より深く知ること 商品配置について | 販売が行えそうな商品 グループワーク |
| 総合職 | 9月下旬 | 1日 | オンライン | 課題解決型 グループワーク | ヘアケアに関する課題解決 個人ワーク ディスカッション |
| 営業 | 7月下旬 | 5日 | オンライン | 公共向けの営業 体感ワーク | 最終日プレゼン |
| 営業、SE、コンサル | 8月中旬 | 5日 | オンライン | 市の活性化につがる 新規事業立案 | 課題の抽出と事業立案 導入までのスケジュール |
| 総合職 | 2月下旬 | 1日 | オンライン | 経営企画 | 課題解決型グループワーク コンビニの新しい取り組み案 |
| 技術職 | 9月上旬 | 5日 | 現地 | 半導体におけるエレクトロ マイグレーションの影響 | 会社説明会 施設紹介 工場見学と実験 発表準備と発表 |
| 営業職 | 9月中旬 | 1日 | オンライン | お菓子売り場の提案 | 業務理解の座学 グループワーク |
| 事務職 | 12月中旬 | 1日 | オンライン | 事前に設定された顧客に 適した住宅選びと オプションの追加提案 | 業界説明 グループワーク 発表 |
| 総合職 | 8月下旬 | 1日 | オンライン | 事業成長を描く | ビジネスの体感 職種の役割理解 魅力の言語化 |
| アプリエンジニア | 9月中旬 | 5日 | オンライン | フードロスを削減するため アプリの企画と開発 | 企画と設計の立案作成 内容の発表 |
インターンシップ先の判断基準
学生がインターン先を決定する際に重要視する内容には、以下のようなポイントがあります。
| インターンシップの期間とスケジュール | インターンシップの期間が自身の学業や他の予定と調整しやすいかどうか。短期か長期か、フルタイムかパートタイムかなども重要なポイントです。 |
| 業界および職種の適合性 | 自分の興味や専攻に関連する業界や職種であるかどうか。将来のキャリアに直結する分野で経験を積みたいと考えることが多いです。 |
| キャリアパスと就職の可能性 | インターンシップが終了後にその企業での就職の可能性があるかどうか。また、インターンシップ経験が他の企業での就職活動にどの程度有利に働くかも考慮します。 |
| 実務内容と学びの機会 | インターンとして担当する業務がどのようなもので、どの程度の実務経験が得られるか。また、どのようなスキルを学ぶことができるかを重視します。 |
| 指導とサポート体制 | メンターや上司からのサポートがどれだけ受けられるか、また、フィードバックがどのように行われるかを重視します。学びの機会が豊富なインターンシップは魅力的です。 |
| 過去のインターンシップの評価 | 以前にその企業でインターンを経験した学生の評価や口コミも重要です。ポジティブなフィードバックが多ければ、安心して応募できます。 |
| 企業文化と職場環境 | 企業の雰囲気や職場の人間関係、働きやすさなども重要です。インターンシップの期間中に自分が快適に働ける環境かどうかを考慮します。 |
| 勤務地と通勤の便 | インターン先の所在地や通勤の便も考慮されます。通勤時間が長すぎる場合や通勤費が高額になる場合は敬遠されることがあります。 |
| 企業の規模や知名度 | 大手企業や有名企業でのインターンシップは、履歴書に記載する際の価値が高いと考えられるため、これを重視する学生もいます。ただし、中小企業でも実践的な経験が得られる場合は人気があります。 |
| 報酬や福利厚生 | 報酬の有無や金額、交通費や食事補助などの福利厚生も重要な要素です。特に生活費を賄う必要がある学生にとっては、重要な判断基準となります。 |
これらの要素を総合的に考慮し、自分にとって最も価値のあるインターンシップ先を選ぶことが一般的です。
応募が少ないインターンシップの共通点
インターンシップが人気がない理由には、以下のような要因が考えられます。
| タイミングやスケジュールの問題 | インターンシップの期間やスケジュールが学業や他の活動と重なる場合、参加が難しいと感じる学生もいます。特に試験期間中や授業の多い時期に開催されるインターンシップは不人気です。 |
| キャリアパスとの関連性の薄さ | インターンシップが将来のキャリアパスに直接的に役立たないと感じられる場合、学生は他の機会を探すことになります。就職活動に有利にならないと判断されることがあります。 |
| 勤務地や通勤の便 | インターン先が遠方で通勤が不便な場合、学生は参加を躊躇することがあります。特に通勤費が支給されない場合は敬遠される要因になります。 |
| 過去の評判や口コミ | 以前にその企業でインターンシップを経験した学生からのネガティブな評価や口コミがある場合、新たな参加希望者が減少します。 |
| 実務経験の不足 | インターンシップの内容が単純な作業や雑用に終始し、実務経験やスキルの向上に繋がらない場合、学生はあまり魅力を感じません。 |
| 指導やサポートの欠如 | インターンシップ中に十分な指導やサポートが得られない場合、学生は成長や学びの機会を感じられず、参加する意欲が低下します。 |
| 業界や職種のミスマッチ | 学生の興味や専攻と関係のない業界や職種のインターンシップは人気が低くなる傾向があります。将来のキャリアに直結しない場合、参加する動機が弱くなります。 |
| 企業の規模や知名度 | 知名度の低い企業や、小規模な企業のインターンシップは、履歴書に記載する際のアピールポイントとして弱いと感じられることがあります。 |
| 職場環境や企業文化 | 企業の職場環境や文化が合わない、あるいは評判が悪い場合、学生はその企業でのインターンシップを避けることがあります。 |
| 報酬の欠如 | インターンシップに報酬が支払われない、あるいは報酬が非常に低い場合、学生は生活費や学費を賄うためにアルバイトを優先せざるを得ないことがあります。 |
これらの要因が重なることで、特定のインターンシップが人気を集めない結果となることがあります。
インターンシップの認知方法
インターンシップへの申込者を増やすためには、効果的な告知方法と魅力的な内容のアピールが重要です。以下に具体的な方法を提案します。
- ◼️ 学校との連携
-
キャリアセンターを活用 キャリアセンターにインターンシップ情報を提供し、学生への告知を依頼します。キャリアセンターのウェブサイトや掲示板に情報を掲載してもらうことも効果的です。 講義やセミナーでの紹介 関連する学部や講義でインターンシップのプレゼンテーションを行う機会を設けてもらう。 - ◼️ オンラインプラットフォームの活用
-
求人サイトやインターンシップ専門サイト リクナビ、マイナビ、インターンシップガイドなどの求人サイトに情報を掲載します。 学校のオンラインポータル 求人掲示板やオンラインポータルにインターンシップ情報を投稿します。 - ◼️ ソーシャルメディアの活用
-
企業のSNSアカウント X、Facebook、Instagramなどの公式アカウントでインターンシップ情報を発信します。特に学生が多く利用するプラットフォームを重視します。 インフルエンサーとの協力 学生に影響力のあるインフルエンサーや学生団体に情報をシェアしてもらいます。 - ◼️ イベントの開催
-
オープンハウスや説明会 企業のオフィスでオープンハウスや説明会を開催し、直接学生にインターンシップの内容を説明します。 キャリアフェアや合同説明会 大学や地域で開催されるキャリアフェアや合同説明会に参加し、直接学生にアプローチします。 - ◼️ リファラル(紹介)
-
インターン経験者の声を活用 過去のインターンシップ参加者に体験談を共有してもらい、SNSやブログで発信します。 社員による紹介 社員やインターン経験者が学生に直接インターンシップを紹介するプログラムを作成します。
これらの方法を組み合わせて活用することで、より多くの学生にインターンシップ情報を効果的に届けることができます。
申込数を増やすヒント
インターンシップの応募者数を増やすために、企業が発信する内容で特に力を入れるべき点には以下のようなものがあります。
- ◼️ 具体的な内容とメリット
-
業務内容の詳細 インターンシップ中にどのようなプロジェクトや業務を担当するのかを具体的に説明します。日々の業務内容や期待される役割を明確に伝えることが重要です。 学べるスキルと知識 インターンシップを通じてどのようなスキルや知識を得られるのかを具体的に示します。特に学生がキャリアに直結するようなスキルを学べる点を強調します。 キャリアパスのサポート インターンシップ後のキャリアサポートや、優秀なインターン生に対する正社員登用の可能性について触れます。 - ◼️ 企業の魅力と文化
-
企業理念とビジョン 企業がどのようなミッションやビジョンを持っているのかを伝えます。学生に共感を呼び起こすようなメッセージが重要です。 職場環境と企業文化 働きやすい環境、チームの雰囲気、福利厚生など、職場の魅力を具体的に紹介します。社員インタビューやオフィスツアーのビデオも有効です。 - ◼️ インターンシップ経験者の声
-
体験談と成功事例 過去のインターンシップ参加者の声や体験談を紹介します。具体的なエピソードやインターンシップを通じて得た成果を共有することで、応募者の関心を引きます。 社員との交流 インターンシップ中にどのような社員と交流できるか、メンター制度の有無などもアピールします。これにより、インターン生が得られるサポートや成長機会を具体的に伝えます。 - ◼️ 報酬や福利厚生
-
報酬の有無と詳細 インターンシップに対する報酬や奨学金、交通費の支給などについて明確に説明します。金銭的な支援があることは大きな魅力になります。 福利厚生の紹介 ランチ補助、社員割引、オフィスの設備など、学生が魅力を感じる福利厚生を紹介します。 - ◼️ 応募手続きと選考プロセス
-
応募方法の明確化 どのように応募すれば良いのか、応募に必要な書類や手続き、締め切りを明確に伝えます。 選考プロセスの透明性 選考の流れや期間、選考基準などを具体的に示し、学生が安心して応募できるようにします。 - ◼️ 柔軟なスケジュールとサポート体制
-
スケジュールの柔軟性 インターンシップの期間やスケジュールに柔軟性があることをアピールします。学生の授業や試験期間に配慮したプランを提供すると良いです。 サポート体制の充実 インターンシップ期間中にどのようなサポートが受けられるか、メンター制度やフィードバックの頻度などを具体的に示します。 - ◼️ ビジュアルコンテンツの活用
-
写真や動画の使用 オフィスやインターンシップの様子を撮影した写真や動画を使って、視覚的にアピールします。特にSNSでの拡散効果が期待できます。 インフォグラフィックやパンフレット インターンシップの概要やメリットを視覚的にわかりやすくまとめたインフォグラフィックやパンフレットを作成し、配布します。 これらのポイントに力を入れて情報発信を行うことで、学生にとって魅力的なインターンシッププログラムとして認識され、応募者数の増加が期待できます。
戦略会議で役立つツール
インターンを成功させるためには、インターン内容の企画とインターンの認知と申し込みまでの仕組みを構築することが重要であることが理解できたいと思います。内部で戦略会議などで役立つツールをご紹介します。
テーマを設定したら思いついたアイデアを発見するフレームワークになります。メリットは自由な発想で色々なアイデアが生まれる可能性がありますが、デメリットは基本知識や経験が不足していると、アイデアが生まれにくくなります。その場合は情報収集スキルを活用して、Web上にある情報で補足しましょう。

自由な思考でアイデアを出し合う
【ブレインストーミング】
1950年頃にアメリカ広告代理店副社長のアレックス・オズボーンという人物によって考案されたものです。考えが入り交じって連鎖反応が起こることで、これまでになかった新しいアイデアが生まれる可能性があります。

回覧板式に発想シートを回す
【ブレインライティング】
複数人で実施します。回覧板式にアイデア発想シートを回して、アイデアを引継ぎ合いながら広げていく手法です。参加者全員がアイデアを書くことになりますので、必然的にたくさんのアイデアを出すことができます。

短期間で顧客体験の検証ができる
【デザインスプリント】
短期間かつ低コストでアイデアのニーズ検証や、プロトタイプを用いた顧客体験の検証ができるため、スピード感のあるマーケットインが求められるデジタル領域における新規サービス開発においてよく用いられます。
一つのテーマを中心に関連したワードをピックアップして、新たなアイデアを発見するフレームワークになります。メリットは連動性があるので、イメージがしやすくスピーディに進みますが、デメリットはありきたりの内容だけで終わることになります。マーケターシンキングによって視点を切り替えてみましょう。

関連する言葉やアイデアを線で結ぶ
【ウェビンマップ】
中心となるテーマから関連する言葉やアイデアを線で結んで広げていく思考整理の方法です。 頭の中で考えていることを、そのまま近い形で書き出すことで、考えや記憶、アイデアの整理がしやすくなります。

情報整理と因果関係を解明
【マンダラート】
マンダラートは81個のマス目を埋めていく思考ツールになります。真ん中にある大テーマから派生したアイデアになるので、関連性と連動性も強いので、導入しやすいアイデアを考えたい場合にお勧めです。
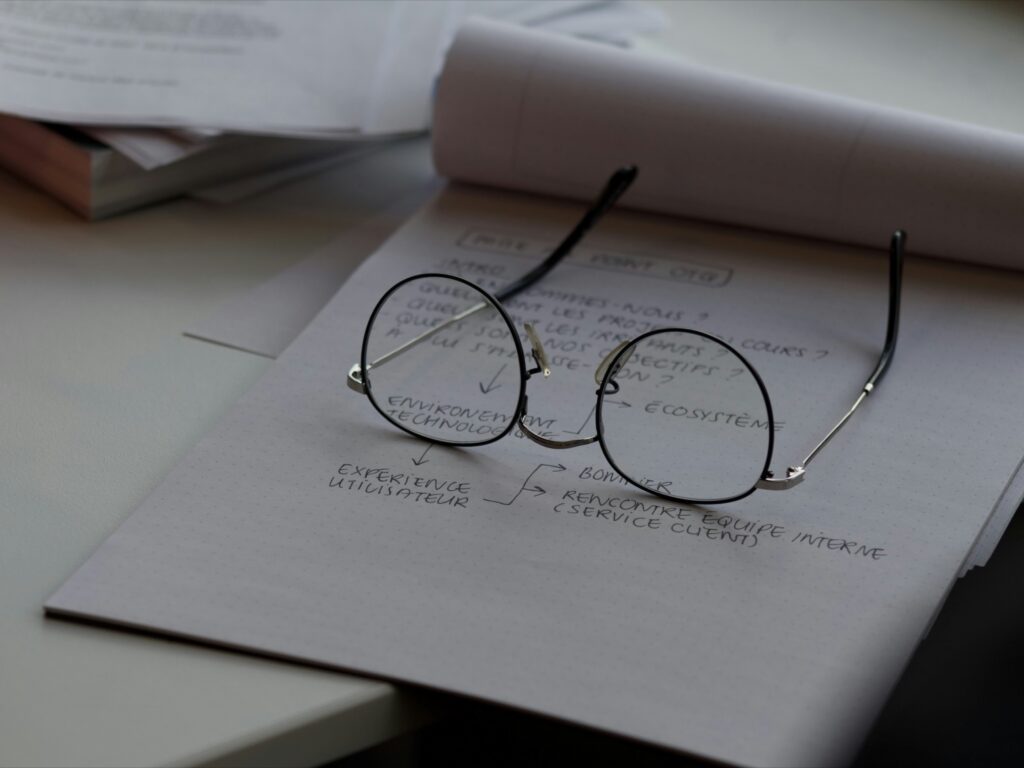
連想ワードで新たな発見
【エクスカーション法】
あるモノの特徴とアイデアを出したいテーマを掛け合わせて連想する方法になります。一人でも簡単にアイデアの発想ができるので、起業家の人におすすめできる発想法になります。
テーマや商品などに対して、条件を与えることで生み出すアイデア法です。メリットは、普段から気になっていることはたくさん出ますが、あまり関連しておらず経験が浅い分野においては、意見がほとんど出ません。参加してもらうメンバーの選出に注意しましょう。

もっと良くなるアイデア
【希望点列挙法】
希望点列挙法とは、「こうすればより良くなる」というアイデアをなるべく多く書き出し、その中から現実味のあるものを抽出したうえで磨き上げていく手法です。外部環境や内部環境を気にしない発想が新しい企画や改善策が発見できます。
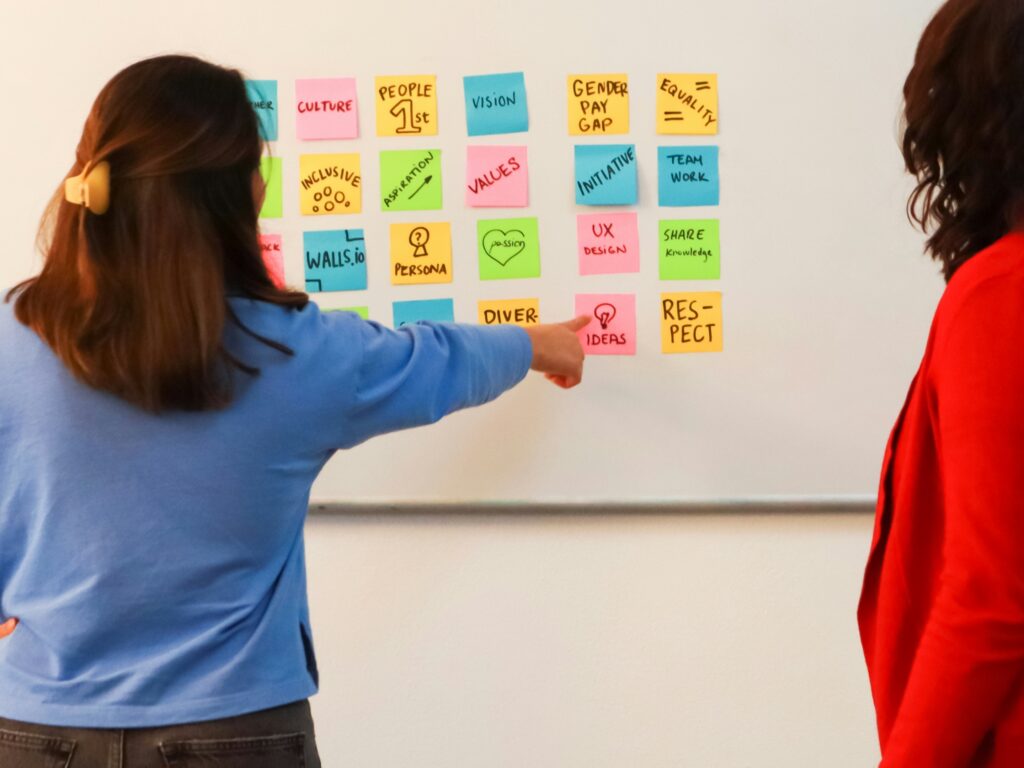
マイナス面から掘り起こす
【欠点列挙法】
検討テーマの欠点や短所、デメリットなどネガティブな点を最初に明らかにしていき、それらのネガティブな要素についての解決策を検討する方法になります。私たちにとってはマイナスでも顧客にとっては価値になることもあります。
顧客にとって大量に情報があるということは、Webにはアイデアのヒントがたくさんあります。メリットは、成功事例を参考にできるので、アイデアを短時間で生み出すことができますが、模倣ばかりしていると特徴がなく、ネットでも指摘されます。自社の強み整理して独自性を必ず取り入れましょう。

Webにある顧客の声からヒント
【ソーシャルリスニング】
Web上にあるブログやSNSには、利用する前の不安や実際に利用した際のメリットや残念な部分を指摘しています。リアルな感想や指摘を収集して分析することで思わぬ発見につながります。

類比した中からヒントを得る
【アナロジー】
類比である機能・性質・構造などが同じ部分の特徴を探し出して、新たなアイデアを発想する方法です。ステップがはっきりしているので誰でも簡単に取り組むことができます。
ペットボトルはドリンクの容器ですが、世界中で様々な再利用がされています。容器の形を生かしものからキャップを閉めることを活用した物など様々です。発想の転換によって新たなアイデアを生み出すことができますが、経験が全くない場合は想像ができません。参加するメンバーの選出が重要です。

課題と逆の解決策を考える
【アンチプロブレム】
「課題と逆の解決策を考えるアイデア発想法」です。課題を直接解決する方法ではなく、正反対の課題を想定し、その解決策を考え、本来の課題に対する解決策の糸口を見つけることが目的です。
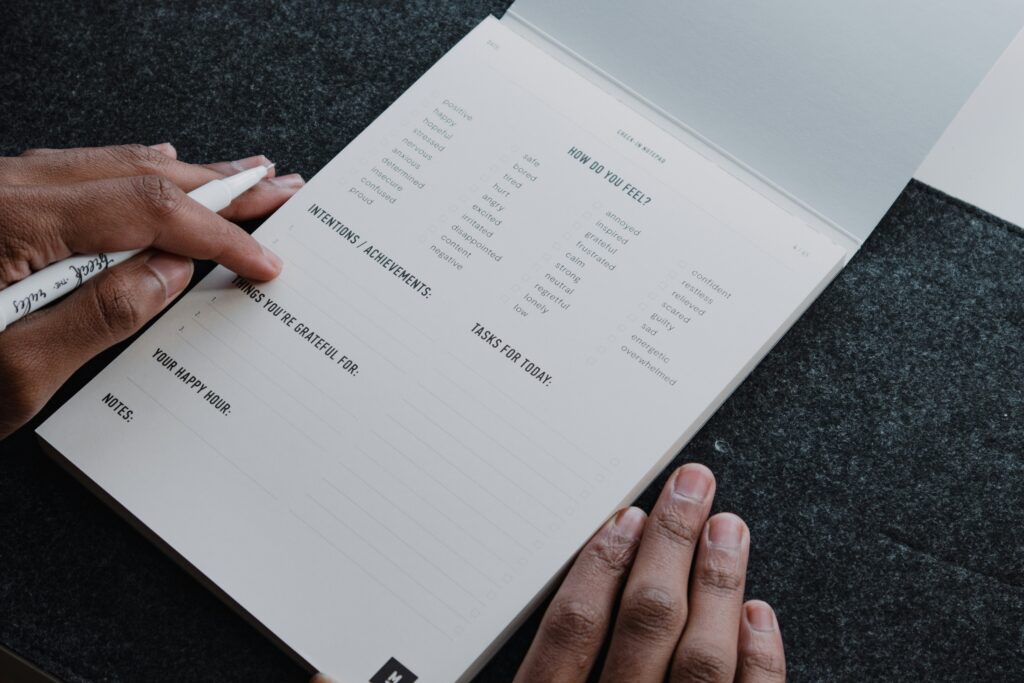
答えるだけでアイデアを発想
【オズボーンのチェックリスト】
あらかじめ用意された質問に答えるだけで、これまで気づくことができなかった発想や視点でアイデアを発見することができます。誰でも手軽に取り組むことができるので初心者向けです。

短時間でアイデアが量産
【SCAMPER】
7つの質問リストに回答していくだけでアイデアを広げることができる手法なので、誰でも手軽に参加することができます。限られた時間の中で効率的なアイデアの創出した場合にお勧めです。

6つの視点で議論が活発になる
【シックスハット法】
6つの色(帽子)にはそれぞれの役割があり、色を担当者した人は与えられた視点(立場)で議論に参加をします。同じようなアイデアばかりで煮詰まってしまうことを防ぎます。

コストを抑えて価値を高める
【ERRC】
バリューイノベーションでは、同業他社が力を入れている部分を把握して、他社が重要視していていない部分で自社の独自性を発揮できるアイデアを発見し、競争を避けると同時に差別化を図ります。
収集したアイデアを目的に合わせて整理する際に活用できるフレームワークになります。

誰でも効率的に収束できる
【KJ法】
KJ法はさまざまなアイデアを効率よくまとめることができるだけでなく、アイデア同士の関係性が見えてくることで、今まで自分たちが考えられなかった思わぬ発見に繋がる可能性があります。

トレードオフの決断に役立つ
【Pros&Cons】
どちらか一つしか選択できないトレードオフが前提とする場面において、自分の意見とは真逆の選択肢についてもメリットを考える必要があるため、思いもよらないアイデアが浮かぶ可能性があります。

問題や原因の発見が容易になる
【ロジックツリー】
ある事柄に対して問題や原因など、その事柄を構成している要素をツリー状に書き出すことで、解決法を導き出すフレームワークです。問題を可視化して分解することによって、複雑な事柄を捉えやすくなります。

原因と結果の関係性を見える化
【フィッシュボーン】
一つの結果を生み出す原因は一つではないケースがほとんどです。これらの様々な要因の関係性を可視化した特性要因図は、その形が魚の骨に似ているところから「フィッシュボーンチャート」とも呼ばれます。

優先順位が整理できる
【セブン・クロス法】
メンバーが課題解決のために共通理解するときなどに効果的な収束技法になります。出てきたアイデアを整理して優先順位をつけ、まず何をすべきかを明らかにすることができます。

ポジショニングや優先順位の判断
【マトリクス分析】
状況がひと目で判断できるため、会議やプレゼンにおいて相手を説得したいときにも有効です。情報を視覚的に伝えることで、ビジネスの戦略や方向性を組織内外に共有しやすくなります。
まとめ
今回はインターンシップの申込者数を増やすためのポイントについて解説してきました。採用については、どれだけ早期に学生との接点(タッチポイント)を設けることができるのかが、希望する学生を確保するためのKSF(key success factor=重要成功要因)になります。
もちろん、人気があるインターンを模範にすることは近道になりますが、中小企業が大手企業と同じ戦略で挑戦しても、資金力や知名度によって厳しい戦いになります。大手にはできない中小企業だからできるインターンシップ戦略を構築していきましょう。
サービスのご案内
CEVSTYでは、ビジネスに特化したマーケターとクリエイターのスキルを持つ「クリエイティブマーケター」を育成するサービスを展開しています。クライアントの目的や状況に応じて、様々なスタイルの育成を準備しておりまので、サービス内容や特徴については下記よりご確認ください。
弊社では学習するだけではなく、事業に貢献できることを目指しているため、年間でのご契約に限りがございます。ご興味があるご担当者様は取り急ぎ、お問い合わせ等をしていただけると幸いです。

