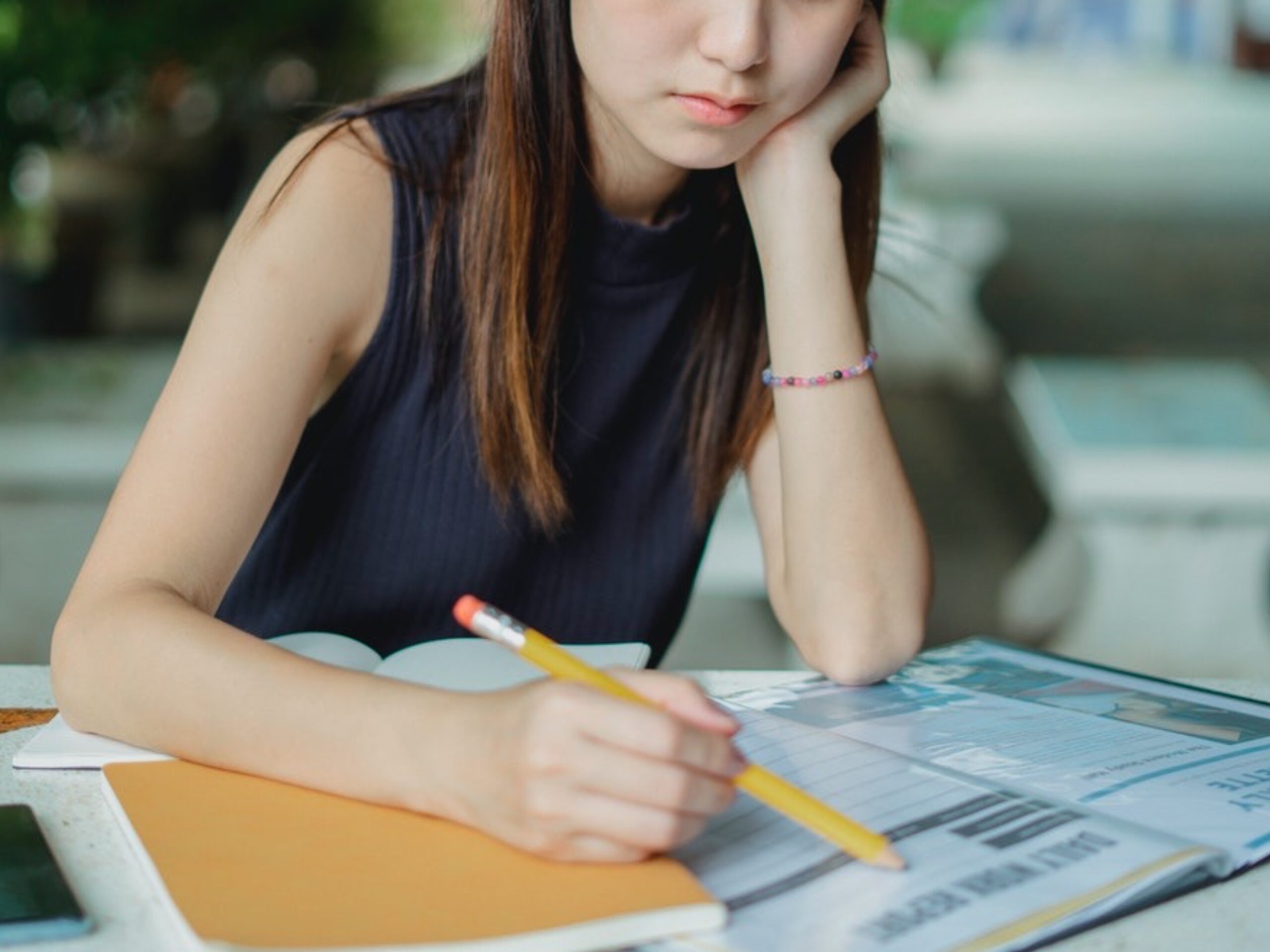これからのビジネスに必須な人材
クリエイティブマーケター
人事担当者や教育担当者は、近年入社してくる学生の指導や傾向に戸惑っていることはありませんか?自分のことなのにどこが人ごとのような振る舞い、言われたことはやるが自分から進んでやろうとしない。これは、その学生さんの性格ではない可能性があります。どのような要因でこのような現象が発生しているのか解説していきます。
学生や新卒に見られる傾向

- 話を長く聞けない
- 集中して聞けない
- メモを取らない
- 自分から聞きにこない
- 自分で判断できない
- 挨拶をしない
このような若者が年々増えていると感じることがないでしょうか。ここでは、近年の学生に見られる傾向の要因について、考えられる背景をご紹介します。
以前の教育現場
以前は、先生が黒板に書いたものを書き写したり、連絡事項も連絡帳に記入して、子供が保護者に先生から言われたことを説明していました。幼少の頃から情報をアウトプットする機会が多くあり、子供自身が理解している部分としていない部分を自己認知し、不明点は自分から質問したり、情報を取りに行く必要性がありました。相手が理解していなければ、説明の仕方やメモの取り方を工夫する学習を日常生活の中で育むことができていました。
常に保護者などへ説明する必要がある状況だったので、人の話を集中して聞き、メモを取り、分かりやすくまとめる習慣が形成されていたと思われます。
メモを取らない
現在は、プリントで配布されたり、iPadや他のデバイスにデータ送信される学校も増えています。連絡事項も保護者用に配布するプリントが毎回用意されています。
そのため、学生たちは保護者が理解してくれているので大丈夫であると思い、話をしっかりと聞いたり、メモを取る意識が弱くなっていきました。他の人が聞いているから、後から教えて貰えばいいと思う学生が増えていったと思われます。メモを取りながら頭で整理して、人に話すことによって理解力を高める機会が少なくなり、語彙力や文章力を伸ばす機会も失われしまったと考えられます。
チャレンジしない
一部を除いて、今の学生さんたちは、大きな失敗や挫折の経験が少なくなっています。それは、保護者をはじめ、教育機関が失敗したり挫折しないように環境を整えているからです。失敗することで得られる悔しさや忍耐力よりも、自信を失う劣等感や自己肯定感を優先するあまり、失敗させない風土になっています。
学校側もチャレンジしたいのですが、安全性や公平性を保つ必要があり、先生の業務も過多になっているため、新しいことに取り組むことができにくくなっています。そのため、学校によっては、教える内容をプリントに全て記載して配布する場合もあります。学生も言われた通りのことをすれば、テストで点数が取れたり、結果がすぐに出ることを覚え、向上心や探究心よりも効率性や生産性を重要視する考えに至りました。その結果、短時間で成果を出す反面、自分達で考える思考力や達成感を味わう機会を失うことになりました。自分で突き進んで勝ち取った経験が少ないため、全てにおいて自信がない学生が多くなっています。失敗してこなかったことが、失敗した場合の不安を増大することになり、チャレンジ精神を持つ学生が少なくなったと考えられます。
情報を取りにこない
場合によってはLINEや専用のアプリで情報発信されています。このことにより、保護者側も情報をしっかりと共有でき、学校側も「聞いていない」と指摘されることがないため、情報は学校側が発信して、子供や保護者は受信する構図が一般的になりました。
情報をもらえることが当たり前の状態になっており、アプリなどもアラート機能でお知らせが届きます。情報をキャッチすることが受け身の習慣になっているため、自分で情報を取りに行く行動が起きにくくなっています。学生さんや新入社員が「聞いていません」と発言するのも、これまで周りは情報を与えてくれていたので、自分で情報を取りに行く考え方に至っていないないからだと考えられます。
挨拶をしない
挨拶はコミュニケーションの第一歩として重要な役割を果たしますが、近年の学生はイヤホンをつけたり、帽子を被るなどして、他者との接触を好まない傾向があります。これは警戒心が強くなっており、知らない人から話しかけれてもうまく会話ができない自信の無さが原因だと思われます。SNSやLINEなどではまったく問題なく話ができるのに、対面になると話ができない学生も多くいます。直接会って話す機会が少なくなっているため、見ず知らず人と初対面で挨拶ができるには、会話ができる自信を持たせる必要があります。
集中力がない
集中力がない大きな原因は、言葉による理解力が乏しくなっていることが考えられます。言葉を聞き取ることや文章を読むことはできますが、言葉の意味を理解していないため、途中から理解が追いつかずに、集中力を保つができていません。SNSなどの動画は見るだけなので、集中して見続けていることから、人の話を聞く集中力は理解力や読解力がないので、話を聞き続けることができず、あくびをしたりキョロキョロしたり、スマートフォンを見てしまう行動を取るのだと思われます。
自分で判断しない
日本の教育では「アクティブラーニング」が推奨されています。アクティブラーニングとは、これまでのように詰め込む教育ではなく、自分たちで考えて問題を解決するような授業スタイルになります。なぜ、このようなスタイルが導入されたのか、それは、自分で考える力が弱くなっているからです。日本には、「失敗は良くない」とする考えがあります。そのため、失敗をしないために情報を収集したり練習を重ねていきます。すでに上達している人から教えをもらうことで、時間の節約にもなり、効率的に習得することができます。一方で習ったことしかやらないため、同じシチュエーションであれば対応できますが、異なる環境や変化が激しい現代社会においては、臨機応変が求められます。失敗をしてこなかった世代であるため、失敗した時の恐怖心は大人になればなるほど大きくなります。自分で判断しないのは、失敗に対する恐怖心の表れです。
まとめ
日本国内では、団塊世代、ゆとり世代、さとり世代、Z世代などと呼び、その世代の特徴を象徴するキーワードを作り上げます。ビジネスにおいて傾向を知ることは重要ですが、世代の人間がすべてキーワード通りの傾向があるわけではなく、ほとんどは、その世代が体験してきたことにより、価値観や知識が異なるだけで、人間の根本的な感情や倫理観などは変わりありません。世代によって経験値が違うだけであり、Z世代から見たら、SNSの使い方が分からない年上の世代の方が役に立たないと思っています。
世代間のギャップを互いに尊重して、得意な部分を補うことが、これからのビジネスにおいて重要なことです。「最近の若い人は」という口癖があるオーナーや管理職がいる会社は、これからの進歩が大きく後退する可能性が高いでしょう。そうならないためにも、若い世代の価値観について新しい情報を収集するようにしてください。